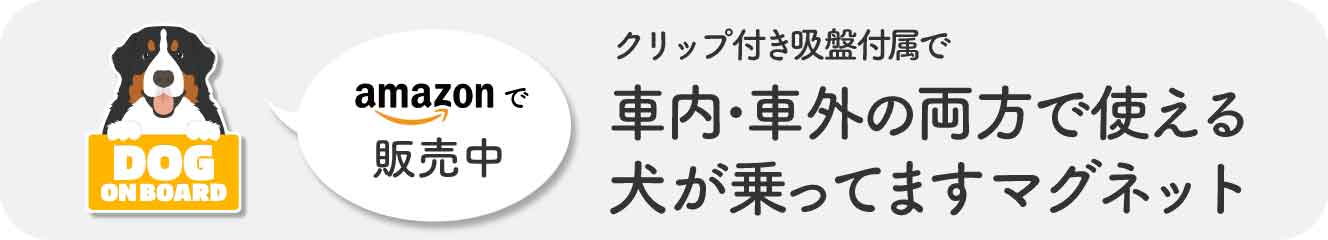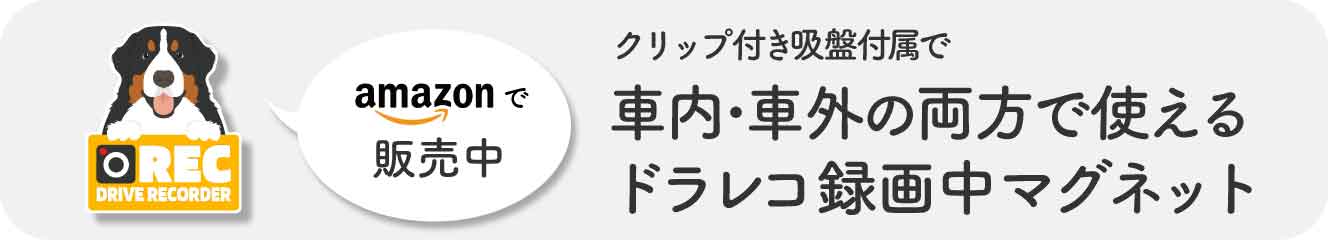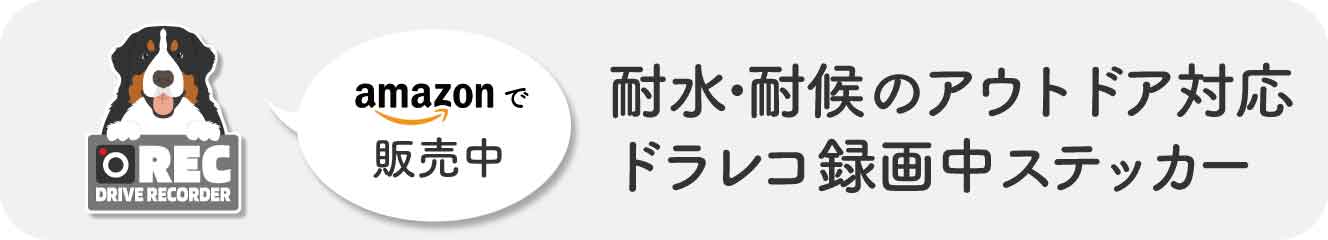高須商店・イメージ
こんにちは。高須商店、監修者の「細峰」です。
バーニーズマウンテンドッグって、本当に大きくて魅力的ですよね。
あのがっしりした体格と穏やかな表情に惹かれる方は多いかなと思います。
でも、バーニーズマウンテンドッグをお迎えしたり、一緒に暮らし始めたりすると、やっぱり「体重」のことが気になってきませんか?
「成犬の平均体重ってどれくらい?」「オスとメスで差はあるの?」「子犬の体重推移の目安は?」「生後6ヶ月でどのくらいが普通なんだろう?」とか、逆に「うちの子、体重が増えないけど大丈夫?」「痩せすぎかも?」なんて不安になったり。
特に大型犬なので、老犬(シニア)になった時のことや、股関節形成不全、胃捻転といった病気のリスクと体重の関係も知っておきたいですよね。
私も大型犬の健康管理にはすごく興味があって、色々調べてみたんです。
この記事では、バーニーズマウンテンドッグの体重に関するそんな疑問や不安について、一緒に見ていきたいなと思います。

ポイント
- バーニーズの成犬(オス・メス別)や子犬の体重目安
- 体重の数値より「体型(BCS)」が重要な理由
- 「痩せすぎ」や「体重が増えない」ときに考えること
- 体重管理が重要な病気のリスク(股関節形成不全や胃捻転)
バーニーズマウンテンドッグの体重目安(成犬と子犬)
まずは、皆さんが一番気になる「標準体重」について見ていきましょう。
でも、実はバーニーズの場合、単純な「平均」がすごく難しい犬種みたいなんですよね。
その理由と、子犬の成長についても掘り下げてみます。
成犬の平均体重(オス・メス別)

高須商店・イメージ
バーニーズマウンテンドッグの成犬の体重、気になりますよね。
私も調べてみたんですが、いろんな情報源で目安が示されていました。
例えば、ある資料だとオスが41kg~54kg程度、メスが32kg~45kg程度という目安があります。
別のところでは、オスが36kg~52kg、メスが32kg~43kgなんていう記述も見かけました。
これ、どっちが正しいの?って思っちゃいますけど、どうやら「どちらも間違いじゃない」みたいなんです。
というのも、バーニーズは大型犬の中でも特に「個体差」が大きな犬種だそうで、骨格の大きさ(体高)によって、ベストな体重が全然違ってくるんですね。
例えば、骨格ががっしりしていて体高も高いオスと、骨格が華奢で体高が低めのオスとでは、理想体重が10kg以上違っても不思議じゃない、ということです。
だから、「平均は〇〇kgです!」って一つの数字で言えないのが現実みたいです。
あくまで、ここに挙げた数字は「一般的な参考値」くらいに考えておくのが良さそうですね。
スタンダードに体重規定はない?
私が調べていて「へぇ!」と思ったのが、犬種の公式な基準(スタンダード)のお話です。
犬種の血統書などを発行している一般社団法人ジャパンケネルクラブ(JKC)や、その上位団体であるFCI(国際畜犬協会)が決めているスタンダードに、なんとバーニーズマウンテンドッグの「体重」に関する具体的な規定って、存在しないそうなんです。
厳格に決まっているのは「体高(地面から肩までの高さ)」だけなんですね。
FCI/JKC スタンダード(犬種標準)における体高
- オス(牡): 体高 64cm~70cm (理想は66cm~68cm)
- メス(牝): 体高 58cm~66cm (理想は60cm~63cm)
(出典:JKC犬種標準書)
じゃあ、なんで体重が決まってないの?っていうと、彼らのルーツが関係しているみたいです。
バーニーズはもともとスイスの山岳地帯で、荷車を引いたり牛の群れを誘導したりしていた「使役犬(ワーキング・ドッグ)」です。
彼らにとって大事だったのは、単なる「重さ」じゃなくて、任務をこなすための「機能的な体の構造」や「力強さ」、そして「バランス」だったんですね。
ポイント
スタンダードの最小サイズ(例:体高64cmのオス)と、最大サイズ(例:体高70cmのオス)が、同じ理想体重であるはずがない、ということです。
だから、「あなたの愛犬の骨格(体高)に対して、筋肉や脂肪がバランス良くついているか」が一番重要、ということみたいですね。
この「絶対的な体重の答えがない」という事実が、次のセクションで触れる「体型(BCS)」による管理が不可欠であることの、一番の理由かなと思います。
子犬の体重推移と成長の目安

高須商店・イメージ
子犬の時期の成長って、ものすごいスピードですよね。
バーニーズも例外じゃなく、生後1年くらいで成犬に近いサイズまで爆発的に大きくなるそうです。
ただ、この成長スピードも本当に個体差が大きいみたいで、あくまで「一例」として参考になるデータがありました。
オス・メスや血統によっても大きく変わるので、本当に「目安」として見てくださいね。
| 月齢 | 体重目安 |
|---|---|
| 2ヶ月 | 約 9.5 kg |
| 3ヶ月 | 約 14.5 kg |
| 4ヶ月 | 約 20.7 kg |
| 5ヶ月 | 約 25.0 kg |
| 6ヶ月 | 約 32.4 kg |
| 1年(12ヶ月) | 約 38.5 kg |
補足
このデータはあくまで一例です。
性別(オス・メス)や血統によっても全然違ってくるそうなので、「この通りじゃないとダメ!」と心配しすぎる必要はないみたいですよ。
この数値より軽いからといって、必ずしも発育に問題があるわけではありません。
生後6ヶ月の体重はどれくらい?
先ほどの表を見ると、生後6ヶ月で約32.4kgとありますが、これはあくまで一つの例ですね。
飼い主さんの中には、SNSやコミュニティで他の子犬の成長記録を見て、「うちの子、生後6ヶ月なのに軽いかも?」「成長が遅れてる?」って不安になる方も多いみたいです。
でも、ここで大事なポイントがあって、バーニーズのような大型犬は、成長期に急激に体重を増やしすぎると、まだ発達途中の関節(特に股関節)にものすごく負担がかかっちゃうそうなんです。
これが将来の「股関節形成不全」という病気の大きなリスク要因になります。
だから専門家の間では、「成長期は、平均グラフに無理に合わせるより、むしろ『痩せ気味(Lean)』に維持して育てた方が、将来の関節の健康には良い」というのが共通認識みたいですね。
子犬の時期にちょっと軽いかな?と感じても、3歳、4歳と時間をかけてゆっくり体が完成していく子も多いそうなので、体重の「数値」だけを追いかけるのは禁物、ということですね。
体重が増えない・痩せすぎの原因

高須商店・イメージ
とはいえ、「体重が増えない」あるいは「痩せすぎ」が心配な場合もありますよね。
まず「痩せている」状態を正しく定義する必要がありますが、これは単に平均体重より「軽い」ことではありません。
獣医学的に心配な「痩せ」とは、次に説明する「BCS(ボディ・コンディション・スコア)」で見て明らかに痩せている(BCS1や2)場合や、普段の体重が短期間で急激に減少した場合(例えば1ヶ月で10%以上減ったなど)を指すことが多いです。
原因としては、大きく2つ考えられるみたいです。
1. 日常生活の問題(カロリー収支)
これはシンプルなお話で、食べる量(摂取カロリー)が足りていないか、運動しすぎて消費カロリーが多すぎると、体重は増えませんよね。
- 摂取カロリー不足 : 特に成長期の子犬は、体を大きくするために大量の栄養を必要とします。フードのパッケージに記載されている給餌量はあくまで「目安」なので、愛犬の運動量や代謝に合わせて調整しないと、量が足りていない場合があります。
- 消費カロリー過多 : バーニーズはもともと運動量が豊富な犬種で、1日2回、各30分~1時間程度の散歩が必要と言われています。これに加えてドッグランで長時間遊びすぎたりすると、消費カロリーが摂取カロリーを上回り、体重が減少することもあります。
フードがその子のライフステージ(子犬用、成犬用)に合っているか、運動量は適切か、一度見直してみるのもいいかもしれません。
愛犬に合ったドッグフードの選び方も、一度チェックしてみるといいかもですね。
2. 病気の可能性(要注意サイン)
こっちが要注意です。日常生活に問題がないにも関わらず痩せていく場合、何らかの病気が隠れているかもしれません。
特に危険なサインとして挙げられていたのが、「食欲は旺盛なのに痩せる」または「しっかり食べているのに体重が増えない(減る)」という状態です。
元気で食欲もあると見逃しがちですけど、これは食べた栄養が「体内で適切に吸収・利用できていない」か、「体内の何か(病気や寄生虫)に栄養を奪われている」ことを強く示唆しているそうです。
注意:食欲があるのに痩せる場合
このサインは、以下の重篤な疾患の初期症状である可能性があります。
- 栄養が奪われる : 悪性腫瘍(がん)、寄生虫(回虫など)
- 栄養が吸収できない : 膵外分泌不全、タンパク喪失性腸症など
- 栄養が利用できない : 糖尿病、腎臓病、肝臓病、心臓病
バーニーズは遺伝的に悪性腫瘍のリスクが高い犬種とも言われています。
もし「食べてるのに痩せる」というサインが見られたら、元気そうに見えても、一度動物病院で相談してみるのが賢明かなと思います。
バーニーズマウンテンドッグの体重管理と健康リスク

高須商店・イメージ
バーニーズの体重管理は、単に太らせない・痩せさせない、というだけじゃないみたいです。
彼らの寿命にも関わる、大きな病気のリスク管理そのものなんですね。
ここでは、体重計の数字よりも大事な「体型チェック」と、注意すべき病気について見ていきましょう。
体重計よりBCS(体型)が重要
セクション1で見たように、バーニーズには「標準体重〇〇kg」という絶対的な答えがありません。
そこで登場するのが、BCS(ボディ・コンディション・スコア)という考え方です。
これは、体重計の数値じゃなくて、犬の「体型」を直接見て、触って、脂肪の付き具合を客観的に評価する国際的な指標だそうです。
例えば、同じ45kgのバーニーズが2頭いたとして、1頭は筋肉質で引き締まっていれば「理想体型(BCS3)」かもしれません。
でも、もう1頭が骨格が小さく、脂肪でブヨブヨしていたら「肥満(BCS5)」と判断されます。
体重計の数字だけを見ていると、この違いを見逃してしまいますよね。
個体差が大きくて、スタンダードにも体重規定がないバーニーズだからこそ、このBCSで「その子にとっての理想」を判断するのが唯一の方法、と言えそうです。
理想体型と適正体重のチェック法

高須商店・イメージ
BCSは5段階評価(BCS1:痩せすぎ~BCS5:肥満)が一般的で、理想は「BCS3」とされています。
ただ、ここでバーニーズ特有の問題があります。
彼らは毛がフワフワの長毛種ですよね。だから、「上から見てくびれを確認」とか言われても、乾いている状態だと毛で隠れて正直よく分からないんです。
太っていても毛並みでくびれているように見えたり、痩せているのに毛量で丸く見えたり…。
そこで一番大事なのが、「触覚(触診)」、つまり飼い主さんの手で直接触って確認することだそうです。
最重要ポイント:肋骨(あばら)の触診
最も信頼できるのが、肋骨(あばら)の触り心地みたいですよ。
日々のスキンシップの中で、愛犬の脇腹を優しく撫でてチェックする習慣をつけると良さそうです。
肋骨の触診チェック
- 理想 (BCS3) : 手のひらで愛犬の胸(脇腹)を優しく撫でたとき、力を込めなくても「薄い脂肪の層の下に、肋骨が一本一本、程よく感じられる」状態。自分の手の甲を軽く撫でた時の、指の骨の感触に似ているそうです。
- 痩せすぎ (BCS1~2) : 脂肪をほとんど感じず、肋骨がゴツゴツと直接手に当たる状態。BCS1だと、見た目にも骨が浮き出て見えます。
- 太りすぎ (BCS4~5) : 手のひらが厚い脂肪の層に阻まれて、肋骨がどこにあるか分かりにくいか、強く押さないと触れられない状態。自分の手のひら(親指の付け根の膨らんだ部分)を撫でる感触に近いかもしれません。
補助ポイント:視覚での確認
触診がメインですが、視覚での確認も補助的に役立ちます。
一番わかりやすいのは、シャンプー後など、毛が濡れて体に張り付いている時です。
この時に、本来の体型がよく見えますよ。
- 腰のくびれ(上から見る): 理想体型(BCS3)では、肋骨の後ろに明確な「腰のくびれ」が見られます。くびれがない、または背中から腰までが一直線の場合は、体脂肪が多いサインです。
- お腹のライン(横から見る): 理想体型(BCS3)では、胸(肋骨)の後ろから股関節(後ろ足の付け根)にかけて、お腹のラインが緩やかに吊り上がっています。このラインが垂れ下がっている場合は肥満傾向です。
股関節形成不全と体重の関係
バーニーズマウンテンドッグと暮らす上で、耳にすることが多い病気の一つが「股関節形成不全」かなと思います。
これは股関節の発育がうまくいかず、関節に炎症や痛みが生じる病気です。
遺伝的な要因も大きいと言われていますが、「体重の負荷」という環境的な要因もすごく大きいそうです。
つまり、遺伝的にその素因を持っていたとしても、体重管理をしっかり行うことで、発症を防いだり、症状を軽くしたりできる可能性がある、ということですね。
特にリスクが高いのが、以下の2つのタイミングです。
関節への2大負荷タイミング
- 子犬の成長期 : まだ骨や関節が柔らかい時期に、急激に体重を増やすこと(=おデブな子犬にすること)。
- 成犬期 : 肥満(BCS4~5)の状態で生活し、常に関節に過剰な負荷をかけ続けること。
子犬の頃は「痩せ気味にゆっくり育てる」、成犬になったら「BCS3の理想体型をキープする」ことが、この病気の発症や悪化を防ぐ一番の対策になりそうですね。
体重管理とあわせて、犬の関節ケアやサプリメントについて知っておくのも良いかもしれません。
胃捻転を予防する食事と体重管理

高須商店・イメージ
もう一つ、バーニーズのような胸が深い大型犬にとって、命に直結する恐ろしい病気が「胃捻転(胃拡張・胃捻転症候群)」です。
これは、何らかの原因で胃がガスや食物でパンパンに膨らみ(胃拡張)、その結果、胃がねじれてしまう(胃捻転)病気だそうで…。
ねじれると、胃への血流が完全に遮断され、周囲の臓器も圧迫されます。
発症すると激しい苦痛(よだれ、吐こうとするけど吐けない「空嘔吐」、お腹が膨れるなど)を示し、数時間以内にショック状態に陥り、命を落とす可能性が非常に高い、ものすごく緊急性の高い病気なんですね。
この胃捻転の最大の引き金とされているのが、「食後すぐの運動」だそうです。
胃に食べ物がいっぱい入った状態で激しく動くと、胃が揺さぶられてねじれやすくなると考えられています。
命を守るための予防策
この致死的なリスクを避けるために、以下の習慣が強く推奨されていました。
- 食事回数を分ける : 1日1回の大食いは、胃が極端に膨らむため非常に危険です。食事は必ず1日2回、できれば3回に分けて与え、一度に胃に入る量を減らします。
- 早食いを防ぐ : 一気に食べ物をかき込むと、空気も一緒に飲み込み、胃拡張のリスクが高まります。早食い防止用の食器(凹凸のあるフードボウル)を活用するのも良い方法です。
- 食後の安静【最重要】: 食事の後は、絶対に運動(散歩、遊び、ドッグランなど)をさせてはいけません。最低でも3時間は、犬が興奮しないよう静かな環境で休ませることが強く推奨されます。
この「運動と食事のタイミング」は、バーニーズの命を守る上で、体重管理と同じくらい重要なんですね。
バーニーズの理想的なルーティン
運動も必要なバーニーズですが、胃捻転と関節のリスクを考えると、
(朝)起床 → 散歩・運動 → 帰宅後、クールダウン(30分~1時間) → 朝食 → その後、最低3時間は室内で安静
(夕)運動(散歩など) → (上記同様)クールダウン → 夕食 → 就寝まで安静
という、「運動が先、食事が後、その後は絶対安静」という生活習慣を徹底するのが、最も安全な健康管理法と言えそうですね。
老犬(シニア)の体重減少ケア
バーニーズは平均寿命が6年~8年とも言われ、他の大型犬と比べてもシニア期を迎えるのが早い傾向にあるようです。
早い子だと4~5歳くらいから、シニアとしてのケアを意識し始める飼い主さんもいるみたいですね。
老犬(シニア犬)になってくると、今度は「体重減少」が心配になってくるケースも多いみたいです。
若い頃と同じ量を食べていても、消化吸収能力が落ちて痩せてきたり、活動量が減って筋肉が落ちてきたり(これは「フレイル」=加齢による虚弱、と呼ばれるそうです)。
ただ、ここで難しいのが、その痩せ方が「単なる老化(フレイル)」なのか、それとも「病気(特にがんや消化器疾患)」が原因なのか、見極めが必要な点です。
先ほど触れた「食欲はあるのに痩せる」サインは、老犬の場合、特に注意深く観察する必要がありそうです。
どちらにしても、シニア犬が痩せすぎると体力や免疫力が低下し、病気にかかりやすくなったり、回復が遅れたりするリスクが高まります。
体重を増やすことが難しくても、「今の体重を維持する」ことを目標に、きめ細やかなケアが大切になってきます。
シニア犬の体重維持ケア
もし愛犬が痩せてきたな、と感じたら、以下のような対策が考えられるそうです。
シニア犬の体重維持ケア
- 食事の見直し : 消化吸収能力が低下しているため、消化しやすい良質なタンパク質や脂質を含んだフード(シニア用、回復期用など)を選びます。
- 食事回数を増やす : 一度に多くの量を食べられない場合は、1日の総給与量は変えずに、食事の回数を3~5回に小分けにして、胃腸への負担を減らします。
- 保温と環境整備 : 老犬は体温調節が苦手になり、痩せるとさらに体温が低下しやすくなります。冷えは胃腸の働きや免疫力を低下させるため、腹巻きやペット用ヒーターの活用、室温・湿度の管理が重要です。
- 適度な運動 : 無理のない範囲での散歩や、室内での軽い運動を取り入れ、筋力の低下(フレイル)を防ぎます。筋肉を維持することは、食欲増進にも繋がるそうです。
バーニーズマウンテンドッグの平均的な体重まとめ
今回は、バーニーズマウンテンドッグの体重について、子犬からシニアまで、そして健康リスクとの関係を見てきました。
私も調べてみて改めて感じたのは、バーニーズマウンテンドッグの体重管理って、本当に奥が深いな、ということです。
単純な「重さ」の管理じゃなくて、その子の「一生の健康」を左右する、すごく重要なことなんですね。
大事なのは、平均体重の「数字」に一喜一憂するんじゃなくて、
バーニーズの体重管理 2つの鉄則
- 愛犬の骨格に合った「体型(BCS)」を、日々触って維持すること。(特に肋骨の触診!)
- 胃捻転予防のために「食後の安静」を徹底すること。(運動が先、食事が後!)
この2点が、彼らの健康寿命を延ばすために、私たちができる一番大事なことなのかもしれません。
特に「食欲はあるのに痩せる」といったサインは、大きな病気を見つけるきっかけにもなり得るので、見逃さないようにしたいですね。
とはいえ、私も専門家ではありませんので、この記事でお話ししたことは、あくまで一般的な情報や目安です。
愛犬のことで少しでも不安や疑問(「うちの子、本当に痩せすぎ?」とか「フードの量はこれでいい?」とか「このBCSの判断で合ってる?」とか)があれば、必ずかかりつけの動物病院の先生に相談してみてくださいね。
大切なパートナーと一日でも長く、健康で楽しい時間を過ごすために、日々の体型チェックと生活習慣、一緒に頑張っていきましょう。